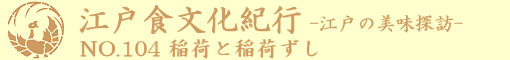|
NO.97で、貼交絵(はりまぜえ)の「東都看立十二箇月」の3枚続きの1枚を紹介しましたが、上の絵もその1枚です。繭玉や花見など1月から4月までをあらわす絵を貼り交ぜてあり、左上の1枚には王子詣とあって王子稲荷社が描かれています。
『江戸名所図会』(1834)には王子稲荷社について「当社は遥かに都下をはなるゝといへども、常に詣人絶えず。月毎の午(うま)の日には殊更詣人郡参す。二月の初午にはその賑ひいふもさらなり。」とあります。
|
| |
江戸時代には中期以降、稲荷信仰が盛でしたが、とくに江戸では『守貞謾稿』(1853)に「江戸にては武家および市中稲荷祠ある事、その数知るべからず。諺に、江戸に多きをいひて、伊勢屋・稲荷に犬の糞、といふなり」とある程でした。また、2月初午の日には前日から賑わい、三都(江戸・京都・大坂)とも、この日は小豆飯に辛し菜の味噌あえをつくって稲荷に供え、人々も食べたとあります。
|
|
稲荷といえば食べ物では稲荷ずしを連想しますが、江戸の稲荷ずしについて『守貞謾稿』には次のように書かれています。「天保末年、江戸にて油あげ豆腐の一方をさきて袋形にし、木茸・干瓢等を刻み交へたる飯をいれて鮨として売り巡る。日夜これを売れども夜を専らとし、行燈に華表(とりい)を画き、号して稲荷鮨あるひは篠田鮨といふ。きつねは油揚を好むもの故に名とす。最も賤価鮨なり。」
|
| |
『近世商賈尽狂歌合』(1852)の稲荷鮨売りの絵には「一本が十六文、半分が八文、一切が四文」とあり、まな板の上には包丁も描かれているので、当時は細長い稲荷鮨を切り売りしていたようです。
なお、きつねを稲荷神の神使とする民間信仰は中世からあったといいます。
|
|
|